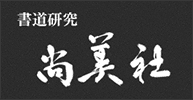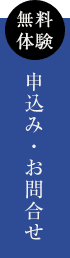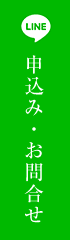SNSで気軽にメッセージを送り合えることが一般的になってきている昨今ですが、贈り物やお祝い、お礼、お詫び、お悔やみなど、便箋で手紙を書く機会もまだまだあります。便箋での手紙の書き方にはマナーやルールがありますので、いざというときに慌てないためにも身につけておくことをオススメします。
そこで今回は、縦書き便箋での手紙の正しい書き方について解説していきます。便箋・封筒・筆記用具の選び方についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
便箋・封筒・筆記用具はどんなものを使うべき?
まずは便箋で手紙を書く際に使うアイテムについてご紹介します。
便箋:一番格式の高いものは「白・罫線なし」
便箋にはさまざまな種類がありますが、格式の高い順では「白・罫線なし」「白・縦書き用罫線あり」「柄入り、カラフルなもの」となります。たとえば、お詫び・お悔やみ・お見舞いなどの手紙を書く際は、お相手に失礼にあたらないよう「白・罫線なし」の便箋を使います。この場合、不幸が重ならないことを願い、便箋の枚数は1枚に収めましょう。
通常の手紙の場合には、1枚の便箋で終わらせないようにするのがマナーです。もし便箋が1枚になってしまいそうなときは、もう1枚の白紙の便箋を「添え紙」として足します。
封筒:便箋とセットになっているものを使用するのがベスト
封筒にもさまざま種類がありますが、便箋とセットになっているものを選ぶと違和感がありません。色はやはり「白無地の和封筒」が基本であり、プライベートからビジネスまで使えるので便利です。
裏紙があり二重になっている封筒がありますが、こちらは個人情報などを書く際に使うといいでしょう。お悔やみ、お見舞い、結婚式のお祝いなどでは、「重なる」という言葉につながってしまうため、二重になっている封筒の使用は避けてください。
筆記用具:用途に合わせるのがマナー
便箋で手紙を書くときに適しているのは、黒やブルーブラック色のボールペン、万年筆です。筆ペンに慣れている方は筆ペンでも大丈夫です。
ただし、お悔やみの手紙を書く際は、濃いインクではなく薄墨色のインクで書くことを覚えておきましょう。「涙が墨に落ちて薄まった」という気持ちを表します。
便箋を書く際に知っておきたいマナーとは
便箋での手紙の書き方には、いくつかのきまりがあります。こちらでは、中でも必ず守りたいものを4つご紹介します。
頭語と結語はセットになっている
「頭語」は最初の挨拶となる「こんにちは」にあたるもので、「結語」は別れを意味する「さようなら」にあたる、手紙上での挨拶言葉です。頭語と結語の組み合わせにはきまりがあり、セットで使います。
| 頭語 | 結語 | ||
|---|---|---|---|
| 一般的なケース | 通常の手紙 | 拝啓 | 敬具 |
| 受取人が目上の場合 | 謹啓 | 謹白 | |
| 受取人が親しい人 急用の場合など |
前略 | 草々 | |
| 差出人が女性の場合 | 通常の手紙 | 一筆申し上げます | かしこ |
| より丁寧な手紙 | 謹んで申し上げます | ||
| 受取人が親しい人 急用の場合など |
|
||
季節の挨拶で季節感を表す
四季がはっきりしている日本では、季節や気候に絡めた挨拶で手紙を書きはじめるのがきまりとなっています。また、手紙の最後では、季節柄に沿って相手の健康を祈る文章で締めくくります。桜の季節、強い日差し、厳しい寒さなど、そのときに合わせて言葉を選びましょう。ただし、お詫びの手紙では、季節の挨拶は省くのがマナーです。
文章の最初は1文字分あけ、行頭をそろえる
小学校の作文の授業で習った方も多いと思いますが、縦書きで書く場合、文章の最初は1文字分あけるのがきまりです。また、改行したあとの行頭もきちんとそろえるようにすると、見栄えがよくなります。
手紙で使うべきではない言葉に注意しよう
行事ごとに使ってはいけない言葉(忌み言葉)がありますので、注意しましょう。
|
行事 |
忌み言葉 |
|---|---|
|
結婚のお祝い |
別れる、切れる、去る、離れる、再び |
|
出産お祝い |
流れる |
|
お祝い事全般 |
朽ちる、古い、乱れる |
|
新築、開店お祝いなど |
火、散る、燃える、倒れる |
|
お悔やみ、お見舞いなど |
また、再び、くれぐれも、重ね重ね |
便箋の書き方(構成)
「お相手が読みやすいように」という思いから、手紙の構成についても「前文・主文・末文・後付け」という順番で書くのが習わしとなっています。では、ひとつずつ見ていきましょう。
前文
前文に含まれるものはこちらです。
- 頭語(拝啓、謹んで申し上げます、など)
- 季節の挨拶(暑い日々が続きますがいかがお過ごしでしょうか、など)
主文
主文では、手紙の目的や用件を書きます。読みやすさを考えて、用件はできれば1通につきひとつが望ましいです。前文から改行し、起語(さて、ところで、など)を入れて主文に入りましょう。
末文
末文に含まれるものはこちらです。
- 季節の挨拶(まだまだ暑い日々が続きますので、どうぞお自愛くださいませ、など)
- 返信依頼など
- 結語(敬具、かしこ、など)
前述の通り、結語については、頭語とセットになっているものを使いましょう。
後付け
目上の方やビジネスなどの手紙を書く際には、後付けを付け足すことが多いです。後付けでは、次のような事柄を書きます。
- 手紙を書いた日付(お祝い事では〇月△日吉日と書いてもOK)
- 差出人の名前
- 宛名(~様、など)
まとめ
縦書き便箋での手紙は、日常生活であまり馴染みのない方も多いかもしれません。お相手に失礼にあたらないためにも、四季が豊かな日本ならではの季節の挨拶や、手紙を締めくくる結語などマナーに沿って書くことが大切です。
書道研究 尚美社では、縦書きの便箋で手紙を書く際に役立つペン字の指導もおこなっております。ペン字の習得は、さまざまな場面で効果を発揮しますので、習っておいて損はありません。どうぞお気軽にお問い合わせください。